土地の価格の基礎
今回は土地の価格について考えてみたいと思います。土地は一物三価あるいは四価、場合によっては一物五価といわれるほど独自の価格体系の上に成り立っています。その概要を見てみましょう。
ひとつのモノに値段が5つ?
モノの値段は需要と供給によって決まるのが基本です。しかし、不動産、ことに土地の場合は金額が高額であること、他の財物に比べて流通性が低いこと、また何より同じ土地は二つと存在しないことなどにより、需要と供給のバランスの観点から価格を把握するのは限界があります。
このようなことを背景に、土地の値段、地価は複数の価格を持っています。まず、公的土地評価には「公示地価」、「路線価」
、「固定資産税評価額」の3つがあり、これを一物三価、つまり一つのモノに3つの価格があることをいい、これに実際に取引された価格である「実勢価格を合わせて一物四価といいます。また、公示地価を補完する「基準値標準価格を入れて一物五価というときもあります。それでは中身を見ていきましょう。
公示地価(地価公示価格)
地価公示法に基づいて、国土交通省が公示する土地価格です。全国に設定された標準地について、毎年1月1日の時点での土地の価格を算定し、3月下旬に公表します。都市計画区域内で選定された標準的な土地が対象です。公共事業の施行者が土地の取得価格を決める際や国土法による土地取引規制における価格審査においては、この公示地価を基準として行うべきとされています。
実施主体:国土交通省
価格判定基準日:毎年1月1日
公表時期:毎年3月下旬
根拠法令:地価公示法
評価の目的:一般の土地取引価格の指標、公共事業用地の取得価格算定、不動産鑑定の基準
調査地点: 23,380地点(平成27年)
路線価
相続税や贈与税などの課税価格を算出するために国税庁が算定する価格です。毎年1月1日時点の価格を評価し、7月1日に公表します。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地価額のことで、路線価が定められている市街地の土地で相続税・贈与税を算定する場合に用います。その土地に借地権がある場合は、借地権割合が90%、80%といったように決められた割合が付与されており、この路線価から更地と仮定した価格にこれらの割合を乗じることにより、借地権価格を算出します(路線化方式)。また、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を用いて算定します。これは倍率方式と呼ばれ、この後に述べる固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を乗じて算出した価格で評価する方法です。なお、路線価は、公示地価の8割程度とされています。
実施主体:国税庁
価格判定基準日:毎年1月1日
公表時期:毎年7月1日
根拠法令:相続税法
評価の目的:相続税・贈与税の算出基礎
調査地点:約362,000地点
固定資産税評価額
固定資産台帳の登録価格のことで、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産に関する税金を課税する場合の根拠となります。市町村が決定し、3年に一度見直しをします。この固定資産税評価額は、公示地価の7割程度とされています。
実施主体:市町村
価格判定基準日:1月1日(3年毎に見直し)
公表時期:基準年の4月頃
根拠法令:地方税法
評価の目的:固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税等の算出基礎
調査地点:全課税土地
以上が公的土地評価の三価です。
実勢価格
実勢価格とは、実際の不動産取引が成立した価格のことで、簡単にいうと時価です。つまり、売り手と買い手の間で需要と供給が釣り合った際の価格をいいます。前述のとおり、不動産は他の財物のように頻繁に取引されるものではなく、また個別の特殊性が強いため、市場価格というものを把握するのはプロでも難しいとされています。そのため取引が行われた場合には、その取引金額が実勢価格になり、いわば“正解”の価格になるわけです。現在ではインターネット等を通じて全国の取引事例から実勢価格を見ることができます。
国土交通省 土地総合情報システム http://www.land.mlit.go.jp/webland/
この実勢価格に前述の公的土地評価の3つを加えたものが一般的に一物四価といわれるものです。
基準値価格
もうひとつ、上で述べた4種類の価格に基準値価格を加えて一物五価という場合もあります。基準地価各は、毎年7月1日における標準的な土地(基準地)を評価し、土地取引の円滑化そして適正な規制を実施するとともに、一般の土地取引価格の指標としても利用されています。公示地価から半年後の地価を評価するものであるため、地価の変動を迅速に把握することで公示地価を補完する役割も担っています。
実施主体:都道府県
価格判定基準日:毎年7月1日
公表時期:毎年9月下旬
根拠法令:国土利用計画法施行令
評価の目的:国土利用計画法による規制の適正化・円滑化 公示地価の補完
調査地点:約21,000地点(平成26年7月1日時点)
このように土地の値段にもさまざまな見方により複数の価格が存在します。不動産を評価する場合は、ここで見た価格をはじめ、いろいろな指標をもとに算定しますが、以前このコラムでも述べたようにプロの不動産鑑定士でも、10人いれば10人とも全く異なった価格をつけることは珍しくありません。それくらい土地は生き物なのです。購入や売却の際は、信頼できる専門家のパートナーを得て、客観的に納得できる価格を把握するよう心がけましょう。






















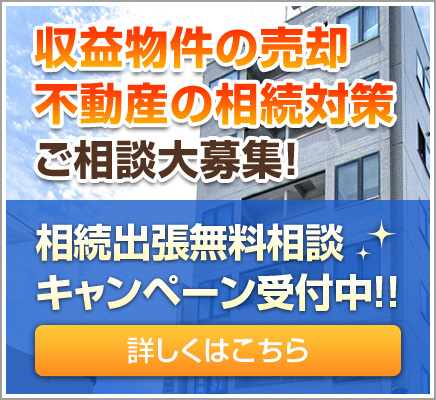
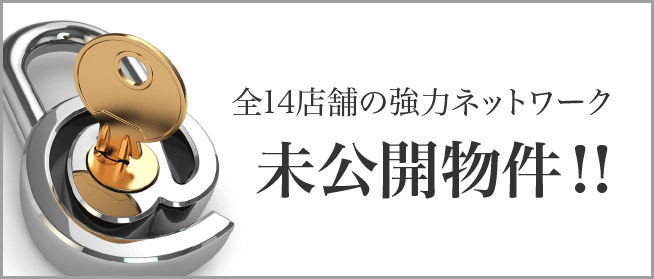
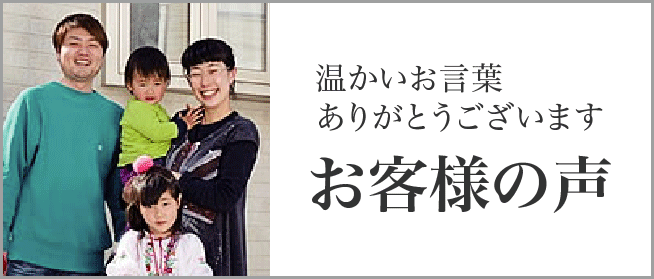



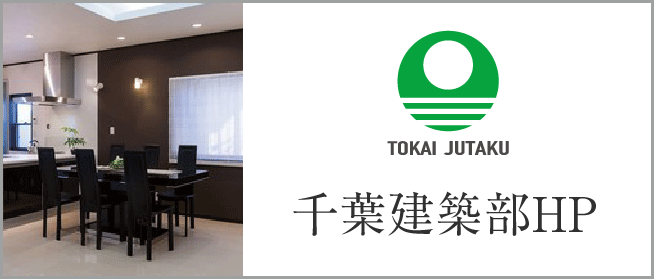
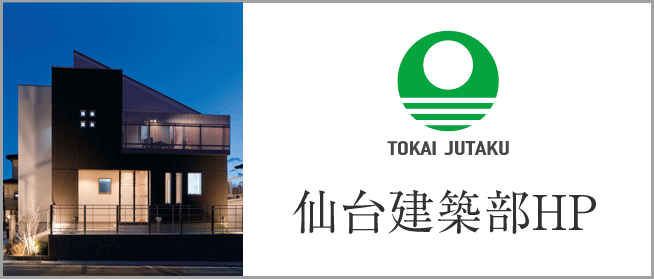


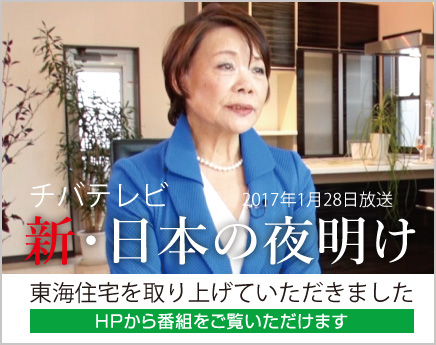

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア