「家の神様」と「大工の神様」
早いもので、2016年もあとわずか。クリスマスのイルミネーションが街を彩り、それが終わると商業施設だけでなく、それぞれの家にお正月飾りが用意されることでしょう。年明けの福袋、休暇を利用しての旅行も楽しみですが、やはり忘れてはいけないのが「初詣」。各地の寺社仏閣には、その年の多幸を祈願する人々が数多く詰め掛けます。
初詣はもとより、私たちは普段、神様、仏さまは寺社仏閣におわすものと認識し、そこへ赴き手を合わせいます。しかし、実のところ神様は「家の中」にもいらっしゃったのです。
「神様が家においでになる?」。現代とは違う年末年始の迎え方
日本には昔から、「新しい年には、その年の幸せを神様に祈る」という風習があります。しかし、今のような初詣が習慣化したのは明治時代からだといわれています。それまでは家長が大晦日の夜から元日の朝にかけ、地元の氏神様で「年籠り(祈願のために氏神の社に籠る行事)」を行い、元旦に来訪する「大年神(大歳神とも。一年間家や家族を災いから守り、福を授ける神様)」様を迎えていました。「門松」や「鏡餅」といったお正月の飾り物は、もともと大年神様を迎えるためのもので、前者は大年神様が来訪するための依代、後者は供え物だったそうです。また「年籠り」は、大晦日夜の「除夜詣」と元日朝の「元日詣」に分かれており、後者が初詣の原形だといわれています。
つまり、江戸時代までは元旦に「大年神(大歳神)」様をお迎えし、氏神様に参り、さらに「恵方参り(その年の恵方にあたる社寺に参詣する)」をしていたのです。「初詣とどこが違う? 同じことでは?」と思う人もいるでしょう。しかし、当時の人たちは氏神様や恵方にある神社を訪れはしましたが、現在行われている「初詣」のように、有名な寺社仏閣に行くことはなかったようです。
家の中にもいらっしゃる、たくさんの神様
「大年神(大歳神)」のように家に来て下さる神様がいらっしゃれば、家の中で住む人を守ってくださる神様もおられます。主にどんな神様がいらっしゃるかというと、
●火之迦具土神:火の神、鍛冶の神様。台所を中心に、火から家を守ってくれる神様。
●三宝荒神:不浄を嫌うことから火の神、かまどの神として台所に祀られている神様。
●大黒天:五穀豊穣、農業、商売繁盛の神様。七福神の一柱。家で最も重要な位置にある「大黒柱(通し柱)」の上に鎮座されているといわれている。
●恵比須:漁業の神、商売繁盛の神様。七福神の一柱。
●天之水分神:水の神、農耕の神、子育ての神様。台所や風呂場など水回りを守る。
●厠神:厠に宿り、主として出産を守護する神様とされている。妊婦がトイレを掃除するときれいな子供が産まれるという伝承も少なくない。
●天石門別神:天の岩戸を神格化した神様。「御門を守る神」であるといわれている。
●納戸神:蔵や納戸、今でいう箪笥や押し入れなど、財産を保管する場所に宿る神様。
●井戸神:井戸を守るために祀られている水神様。
●屋敷神:屋敷およびその土地を守護する神様。地域によっては、「一族を守る」「集落を守る」神様もいる。
などがよく知られています。
上記はほんの一例で、地域によっては呼び名が変わったり、その土地・一族ならではの神様がおわしたり、数多くの神様が家を守っています。「八百万の神」といわれるように、太古の昔から、日本人は海や山をはじめ、石ころひとつにも神が宿っていると考えていました。ですから家の要所に神様の存在を感じるというのは、とても自然なことだったのでしょう。
また、家の神様といえば、真っ先に「座敷わらし」を思い浮かべる人もいるようです。これは子供の姿で座敷や蔵に住む神様、また精霊・妖怪だともいわれ、住み着いた家に富をもたらすと考えられています。東北には「座敷わらしが住む宿」があり、姿を見る(気配を感じる)と幸運が訪れるということで問い合わせが殺到。なかなか予約が取れないといいます。
ただし、座敷わらしが去ってしまうと家は衰退するそうです。そのため座敷わらしのいる家では、お膳やおもちゃを供え、手厚くお祀りしています。
歴史の教科書でも有名な「大工の神様」
家を守る神様がいらっしゃるように、家を作る大工(職人)にも信仰の篤い神様がいらっしゃいます。それは「厩戸皇子(聖徳太子)」です。厩戸皇子といえば推古天皇の摂政で、「遣隋使の派遣」「冠位十二階、十七条憲法の制定」をはじめ、「仏教の興隆」などにもつとめた政治家で、日本史を学ぶ上でも欠かせない人物。それが中世以降、「大工の神様」となったのは、厩戸皇子が世界最古の木造建築として知られる「法隆寺を建立した」こと、大工道具の「曲尺」の単位を1尺(30.3cm)に統一、さらに、材木などの長さ測る、勾配を出すなど計算尺のようにも使える「差し金(指矩など他表記もある)」を考案したからだといわれています。また、かつて「大工」は建築技術者の職階を示し、職人を統率する長とされていたそうですが、それを組織したのも厩戸皇子だと伝えられているそうです。
「差し金無くては雪隠も建たぬ」ということわざがあります。これは「差し金がなければ、トイレすら建てることができない」という意味ですから、これを作った厩戸皇子が「大工の神様」になったのもうなずけますね。
今でも厩戸皇子の忌日である2月22日(地域、組合によって異なる)には、大工をはじめ、曲物師、鳶、左官、建具屋、鍛冶屋、畳屋などの職人が集まり、太子像を祀り、飲食、会合などを催す「太子講」も全国で行われているそうです。











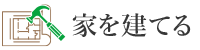


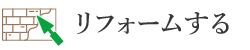







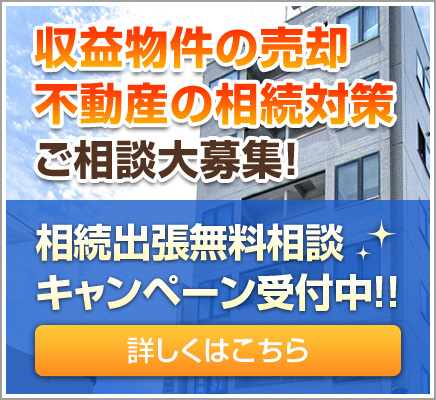
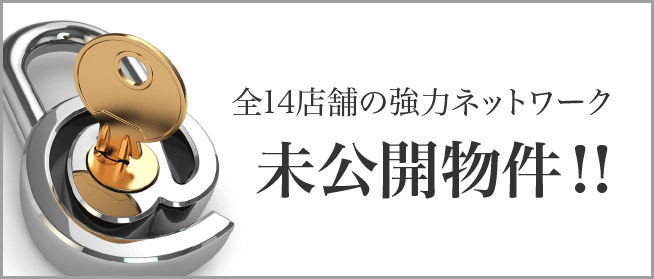
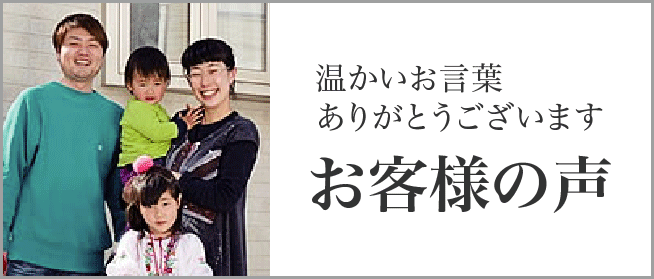



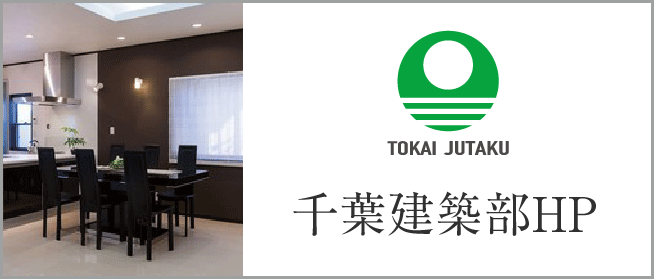
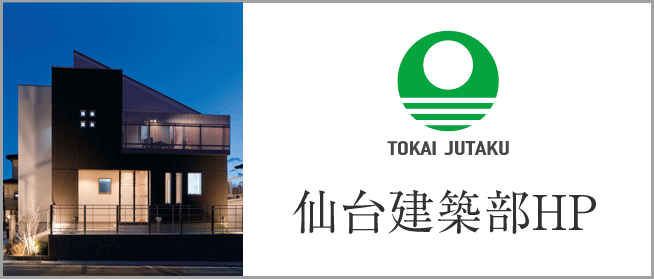


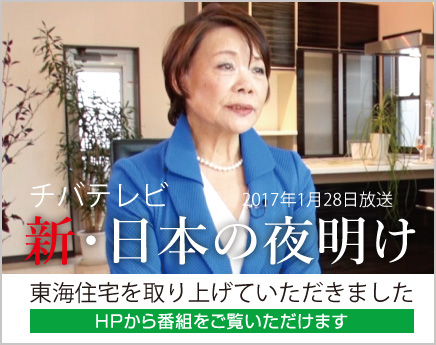

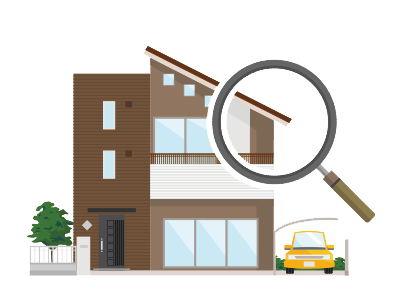 物件を探す
物件を探す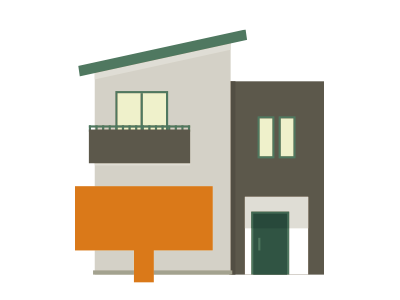 売却の相談
売却の相談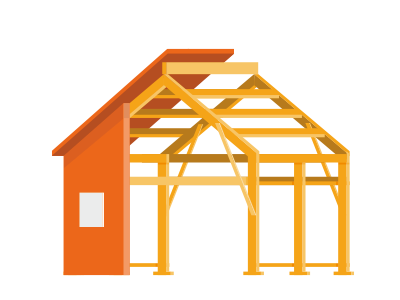 家を建てる
家を建てる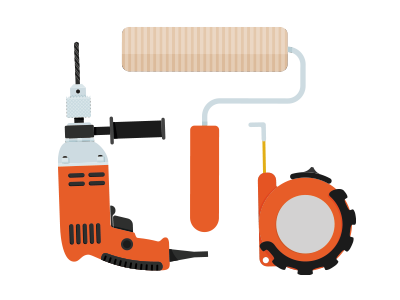 リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア