防災観点から見る建築物の変遷
9月1日は、1923年(大正12年)の同日、「関東大震災」が発生したことを含め、台風の季節を迎える時期でもあることから「防災の日」に定められています。1960年(昭和35年)、「政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しよう(東京消防庁の「消防雑学辞典」)参照」という目的で創設されました。なお、1987年(昭和57年)には、防災の日を含む一週間を防災週間と定め、地方自治体、学校、町内会において、訓練や行事といった様ざまなイベントが行われています。
今回は防災の観点から、日本の建築を見ていきましょう。
文明開化の象徴「煉瓦造り」の建物と関東大震災
江戸から明治へ時代が変わり、その際、日本の街並みも大きく変わりました。政治の中心地となった東京市(当時)は最たるもので、中央区銀座一帯の家屋がすべて煉瓦建築となり、大通りには街路樹が植えられ、その西洋風の街並みは、まさに「文明開化の象徴」となりました。
「銀座煉瓦街」が計画・建設に至ったのは、江戸時代の東京が「火事の多い都市」だったからです。今も「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉が残っているように、数多くの建物が焼失、多大な犠牲者が出た火事が十数回も起きています。よく知られているのは「明暦の大火」「天和の大火(お七火事)」「明和の大火」「文化の大火」などですが、このうち「明暦の大火」では10万人以上、「明和の大火」では約1万5000人が犠牲になりました。明治時代になっても火事は続きます。江戸~初期東京で火災が多発した原因は、木造家屋が狭いエリアに密集していたこと、「竜吐水(木製手押ポンプ)」は配備されていたものの水での消火は難しく、「破壊消防(周辺の建物を壊し、延焼を防ぐ方法)」に頼らざるを得なかったことなどがあげられます。
火災の多さを憂慮した明治政府は、東京市中の全家屋を石造りとする「燃えない都市作り」を試みます。その手始めが銀座煉瓦街の建設だったのです(ただし、すべて市街地を煉瓦作りにするという計画は、資金不足で頓挫してしまいました)。
関東大震災で倒壊した「浅草凌雲閣」
一応の完成を見た「銀座煉瓦街」ですが、市民には高価であったこと、昔ながらの木造建築、畳での生活を続けていた人々にとって、煉瓦家屋は不評だったそうです。そのため、なかなか借り手がつかず、場所によっては空き家も多かったといいます。しかし、新聞社(朝野新聞:現在の朝日新聞)や輸入商品店、時計店、現在も続く「木村屋(パン)」、「鳩居堂(文具)」などが煉瓦街に集まったことで、銀座は江戸時代と同じく、商業地として発展していきました。また東京駅、上野図書館、赤坂離宮、地方では富岡製糸場、赤レンガ倉庫をはじめ、各地で大規模の煉瓦建物も建てられるようになります。
当時のシンボル的な煉瓦建築といえば、やはり「浅草凌雲閣」でしょう。明治20年代になると、高い場所から眺望が楽しめる「望楼建築」が人気を博し、1889年(明治22年)、大阪に「凌雲閣」、その翌年には浅草凌雲閣が建設されました。高さ約67m(10階まで煉瓦造り、11・12階は木造)、建物内には諸外国の物品販売店、休憩室、眺望室などに加え、1~8階には日本初のエレベーターを設置。今でいえば東京タワーやスカイツリーといったところで、多くの観光客を集める、歓楽街・浅草のランドマークとなりました。
しかし、煉瓦建築の時代は、それほど長く続きませんでした。1923年(大正12年)9月10日に発生した「関東大震災」によって、多くの建物が倒壊してしまったからです。浅草凌雲閣は8階で折れるように潰れ、横浜においても煉瓦造の横浜地方裁判所が倒壊しています。銀座煉瓦街は資料によると全壊家屋はなく、亀裂の入った建物が20棟でした。このことから、最低限の耐震性はあったことがうかがえます。ただ、建物が木造骨格だったため、外壁破損によって火の粉が木に燃え移り、これが震災火災につながってしまいました。
関東大震災で壊滅的な被害を受けた煉瓦建築は、耐震性の問題で需要が激減。小規模建築にとどまり、代わりに鉄筋コンクリート造が主流になっていきます。
防災性の高い家作りを目指し、進化する木造建築
大規模建築が鉄筋コンクリートで作られていくのに対し、一般の家は昔ながらの木造建築でした。第二次大戦後、日本は「火災に強いまちづくり」を目指し、1950年(昭和25年)には建築基準法が制定されます。この時、大規模木造建築に対しては、強い規制がかけられるようになりました。さらに戦後復興期だったため、大量の木材伐採によって森林資源の減少が危ぶまれたことから公共建築物の非木造化が進み、一般建築でも同様の流れが生じます。
しかし、2000年(平成12年)の建築基準法改正において規制が緩和され、定められた性能を有する建物であれば、多様な建築計画・構造計画が可能になり、建築物の耐火性能が証明できるのであれば、大規模な木造建築も許可されるようになりました。
近年、人と環境に優しい木造の家の快適さ、住みやすさが見直されています。ただし,木材には「燃えやすい」という性質があります。これを克服する技術や研究により、その点を克服する内装・外装材、構造材も増えています。新築で家を建てるのであれば、火災をはじめ、防災面を見据えておくといいでしょう。






















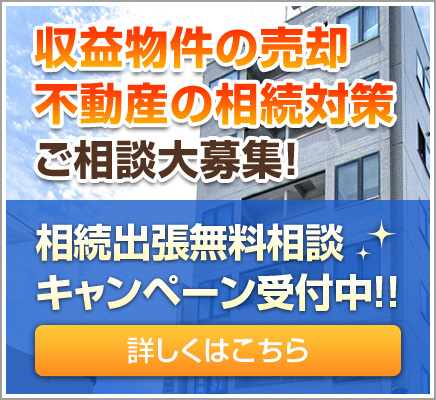
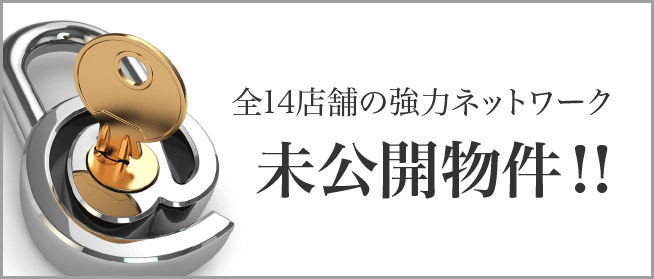
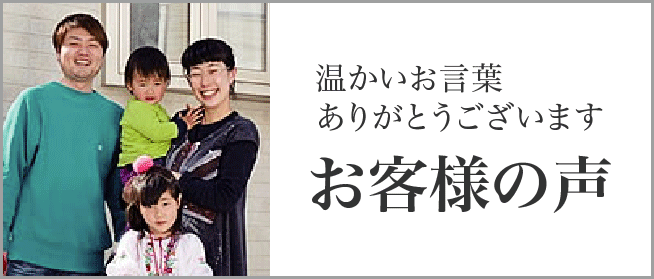



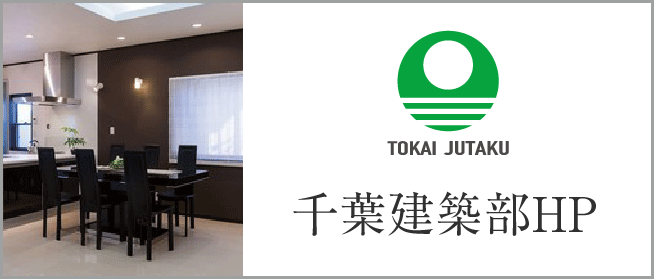
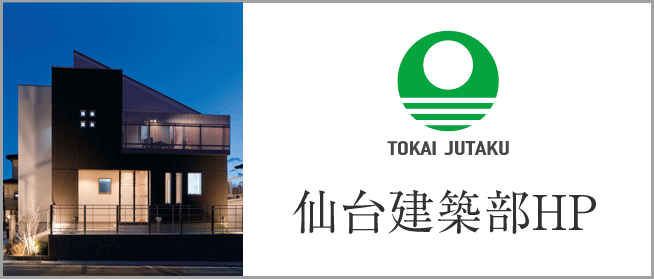


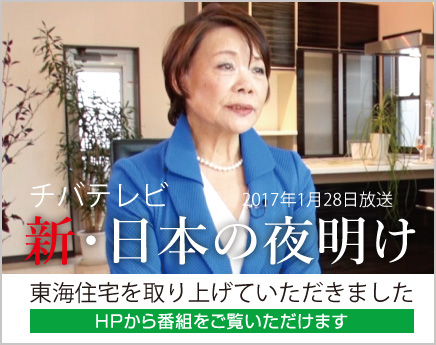

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア