建築協定 住民が作るわが街の約束
今回は建物の用途などについて、住民が協力してその街独自のルールを作る仕組みである「建築協定」について取り上げます。
建築協定とは
建物を建てることについては、今までも何度か取り上げてきたように建築基準法がその法的な根拠となっています。建築基準法は国が作った法律ですが、それとは別に住民がその地域ごとに建物の用途などについて独自のルールを作る仕組みがあります。これが今回ご紹介する建築協定です。建築基準法は全国共通で守られるべき法律であり、地域ごとの事情をすべて網羅しているわけではなく、そこに住む人々の要求もさまざまです。そのため、住宅地としての環境や商店街としての利便性などをより地域に沿ったレベルに維持増進することを目的に、土地所有者などが建築物の基準を独自に取り決めるのが建築協定です。この基準は建築基準法で定められたものに上乗せする高度な基準を定め公的主体(特定行政庁)が認可することで効力が発生します。これによりその安定性と永続性が保証され、住民発意による良好な環境の街づくりが促進することが期待されます。
締結には全員で
建築協定は土地所有者などによる自主的な協定です。しかし全国どこでも自由に作れるわけではなく、市町村が条例で定める区域内に限って建築協定を締結することができます。締結に際しては土地所有者と借地権者全員の合意が必要です。しかし、借地権が設定されている土地では借地権者の合意だけあれば足り、土地所有者の合意は不要です。そして建築協定の内容が決まったら、特定行政庁に申し出て認可を受ける必要があります。特定行政庁とは建築主事が置かれる地方公共団体のことで、建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を取り扱います。
認可がおりて公告されると、その後に土地所有権や借地権、建物賃借権を取得した人についても建築協定の効力が及びます。これを第三者効といい、協定締結の当事者以外の第三者がこの協定の目的となっている土地などを取得した場合にもこの第三者を拘束する効力です。住民が決めたルールがある土地に新たにやって来た人もそのルールは守らなければならないとするものです。ただし、合意していない底地権者から底地権を引き継いだ者には効力がないとされています。
また、建築協定が結ばれた区域に隣接した土地で、将来的に建築協定の一部となることが望ましい土地については、その後にその土地の所有者が簡素な手続きで協定に参加することができます。このような土地を建築協定区域隣接地といいます。
一人で決めることも可能?
前述したように建築協定は土地所有者や借地権者全員の同意が必要ですが、所有者が一人しかいない場合も建築協定を作ることができる「一人(いちにん)協定」という仕組みもあります。これは、ニュータウンなど住宅地を新たに開発する不動産会社が、宅地分譲をする前、つまり不動産会社が一人で土地を所有している場合に建築協定付住宅地として販売する際などに用いられます。1者のみで協定を締結できることから一人協定と呼ばれますが、その反対が合意協定です。現在有効な建築協定地区の約半数がこの一人協定ですが、更新時期を機に合意型に移行するケースが増えてきています。
手続きと運営
建築協定の認可手続きの流れは以下のとおりです。
建築協定条例の制定
↓
地権者の合意
↓
認可申請
↓
申請に係る建築協定の公告・縦覧
↓
公開による聴聞
↓
認可
↓
認可の公告
↓
建築協定書の縦覧
建築協定が結ばれると協定の運営を円滑にし、より実効性のあるものとするため、一般的には区域内の住民による「建築協定運営委員会」を設け、下記のような活動を行っていきます。
・建築計画の審査
・建築工事中、完了後の物件のチェック
・違反があった場合の措置
・啓発活動
・建築協定の更新作業 等
なお、締結した協定の変更や部分的に新しい協定を作る場合も全員の合意が必要です。しかし、廃止する場合は過半数の合意で済みます。また、協定に違反する者がでた場合は、運営委員会は違反工事の停止や是正措置を請求することができます。それでも改善されない時は、裁判所に提訴するなどの措置がとられることもあります。
このように建築協定はその区域に住む人々が主体となって、より地域に根ざしたルールを自主的に決める取り組みによって実現するものです。






















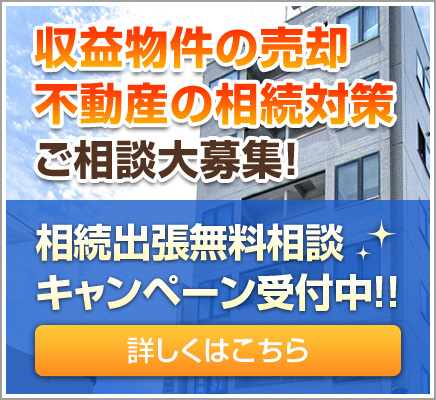
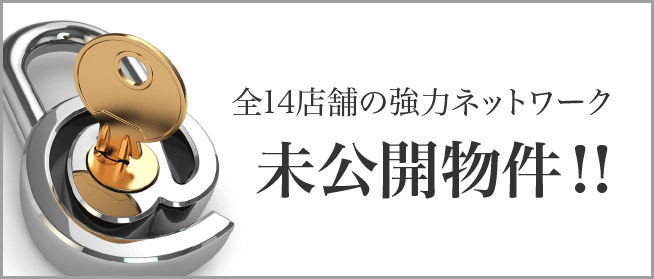
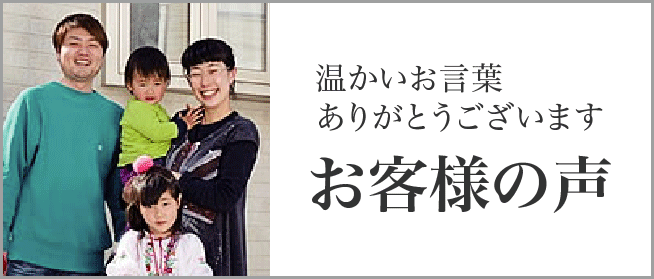



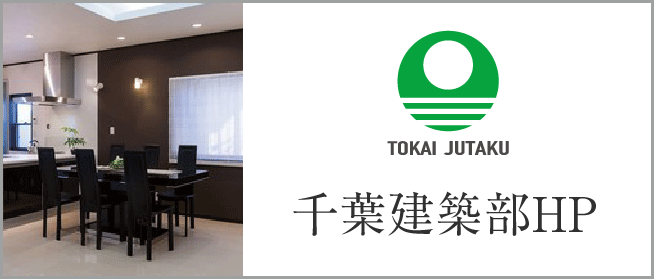
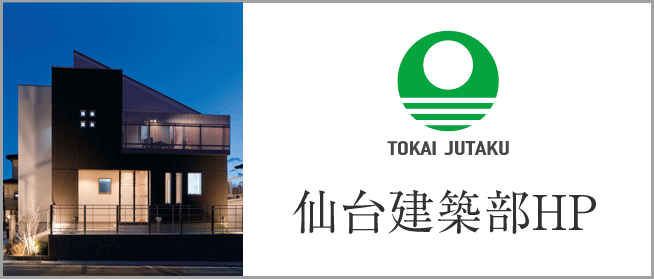


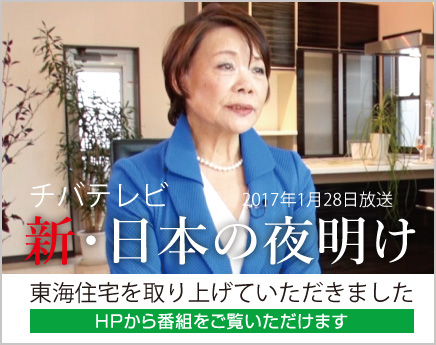

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア