建物に絶対欠かせない「壁」について
建物の外周部分であり、部屋などを仕切る役割も有する「壁」は、一戸建てや集合住宅を含む、建物全般において必要不可欠なパーツです。特に外壁には、音や熱をはじめ、光、風雨、湿気、さらに外部からの視線、泥棒や空き巣の侵入を遮るなど、そこに住む人の暮らしを守る大切な役目があります。そのため、壁自体にいろいろな建材が使われるのはもちろん、施工方法で得られる様ざまな性能も求められています。
今回はあって当然、でも、意外と知られていない外壁の歴史、機能や工法について調べてみました。
木造建築主体の日本で発展した「真壁」
壁には大きく分けて、室内と外界とを隔てる「外壁」と建築物内部の各室、また部屋と廊下などの間を仕切る「内壁(間仕切り壁とも)」があります。構法によって「真壁(真壁造とも)」と「大壁(大壁造とも)」に大別され、前者は柱と柱の間に壁をはめ、柱が外から見える様式、後者は柱を内装や外装で包み、柱を見せないような作りになっています。真壁は、木造住宅の壁に多く見られる伝統的構法で、洋風建築が主流の現代においても、和室には真壁を施す家は少なくないようです。真壁は外壁にも用いられており、その場合は、隅柱や露出させたい柱を外に出るように配置、または他より大きな柱を利用。外壁の真壁の例としては、犬山城天守などの城郭建築に多く見られ、「長押・長押形」と呼ばれています。
日本で真壁が多く用いられてきた理由のひとつは、古代から木造建築が中心だったからです。温暖多湿な気候風土の日本には、昔から良質の木材が豊富に産出し、それらが家屋にも使用されていました。また、木造建築は通気性に優れているので、夏の暑さを和らげるという効果も期待したのでしょう。『日本書紀(奈良時代の歴史書で六国史の一つ。養老4年(720年)成立)』や『万葉集(現存する日本最古の歌集。全巻の完成は8世紀末頃)』にも建築用の木材についての記述が多数見られ、法隆寺金堂、五重塔をはじめとする古代の建築部材からもわかるように、当時主流とされた木材はヒノキです。ヒノキの持つ強度、仕上がりの美しさ、加工性の高さが、建物作りの条件に合っていたからだと考えられています。また、ヒノキ以外では、飛鳥時代の建立である山田寺でクスの柱が発見され、8世紀の薬師寺東塔、当麻寺西塔では強度が必要な部分的にケヤキを使用。ただし、これらはあくまで補助的なものだったようです。
寺社仏閣の建立はもとより、外国から新たな工法が取り入れられたことで、木造建築技術はさらに発展。12世紀ごろになると、マツやケヤキがなども主要材料として使用され始めます。というのも、当時は社寺造営が盛んで、資源が不足していたからです。これを裏付けるように、鎌倉幕府は東大寺の復興に際し、木材を周防(今の山口県東部)といった遠方地域に求めています。一方、同じ頃に大陸の「貫構造(通し貫とも。柱に横材を貫通させる工法)」が伝来。貫構造を用いることで、建築強度を有する種類の違う建材が併用できるようになったことも、木造建築の進歩と隆盛に拍車をかけたことは想像に難くないでしょう。
生活スタイルによって作り分けられた外壁
日本の外壁は、「登呂遺跡(静岡市登呂にある弥生時代後期の遺跡)」の「板校倉」がルーツといわれる「校倉造(柱を用いず、台形や三角形の木材を井桁に積んで壁にしたもの。東大寺の正倉院や唐招提寺の宝蔵・経蔵などが有名)」など、特に寺社仏閣や高級家屋では「板壁(板張りの壁)」が一般的でした。一方で、約5000年前のピラミッド、古代ギリシャ、ローマの建築物にも使用された「漆喰(消石灰に砂、海藻のり、すさを混ぜて水で練った材料)」の加工技術が、日本にも伝来。「高松塚古墳(7世紀末〜8世紀初頭に築造された円墳。彩色による人物像や四神図などで有名)」や「キトラ古墳(7~8世紀に作られ、皇族あるいは貴族の墓と推定されている)」に漆喰が用いられていることから、約1300年前には、すでに漆喰技術があったと考えられています。
土の壁自体は古代からありましたが、飛鳥時代(6世紀末~7世紀、推古朝を中心とする時代)になると、「土工」「白土師」「灰工」といった職業が登場。奈良時代初期の壁工事には、上塗り用として主に白土(白粘土)が使用されるようになります。鎌倉時代(12〜14世紀)に入ると、奈良時代末期~平安時代初期に登場した土蔵を、より火災に強いものにしようと技術も向上。室町時代(14~16世紀)後期、茶道の普及に伴い登場した「数寄屋造り(茶室建築の手法を取り入れた住宅様式)」の意匠に必要だったことから、土壁は日本家屋に深く浸透するようになります(土壁のほかには、長押を省く、面皮柱や荒壁、下地窓などを用いるといった決まりがある)。また、壁塗工事を行う職人が「左官」と呼ばれるようになったのも、この頃(室町後期の「桃山時代」)からだといわれています。
ただ、姫路城などに代表される漆喰による壁は高価だったため、権力者や豪商・豪農といった富裕層しか利用できませんでした。米のりを入れていた高価な漆喰から、比較的安価な海藻のりを使った漆喰が登場するのは、江戸時代(17~19世紀)のこと。耐火性・耐久性に優れた漆喰塗りが普及し、様ざまな壁や建物が作られるようになります。
江戸時代の主な外壁加工法と特徴
江戸時代以降の壁は、内壁には土壁、漆喰、外壁としては、これに加えて板壁や石などが使われてきました。
・土蔵造り:木部の外側を土壁で覆い、白土または漆喰の上塗りをかけた非常に厚い大壁。日本建築における耐火構造のひとつで、桃山~江戸時代には土蔵だけでなく、民家や寺院建築にも広がった。
・板壁:建物の外壁に、板材を用いて、お互いが少し重なるように張る構法。板を横長に使って張り重ねる「横羽目」と、縦長に並べる「縦羽目」がある。商家などでは土壁や土蔵造りの一部に施す場合も。海岸地方など風の強い所では塗り壁は傷みやすいため、板壁が多用されていた。
・土壁:土を用いて、左官工事によってつくられる壁の総称。貫(真壁において、壁の下地になる水平材)に木舞(小舞とも。細い竹や割り裂いた竹などのこと)を縦横にからめ、それに荒木田(土壁の下塗りに使用する土)を塗って作る。
なお、時代が下って明治、大正時代には煉瓦も用いられるなど、外壁は多様化していきます。






















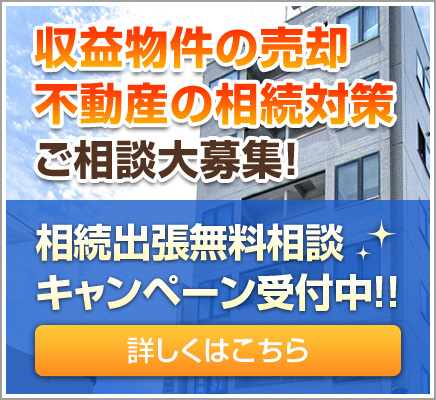
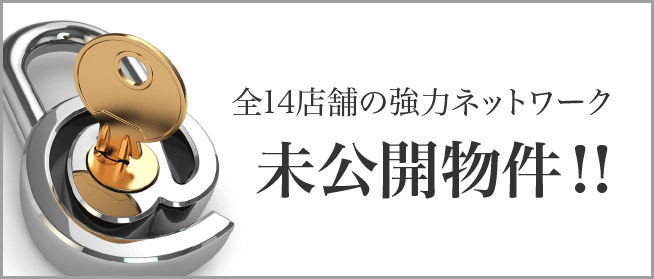
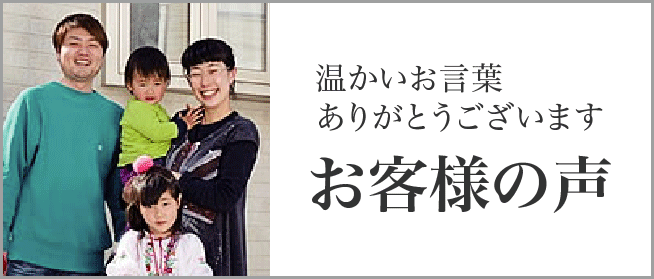



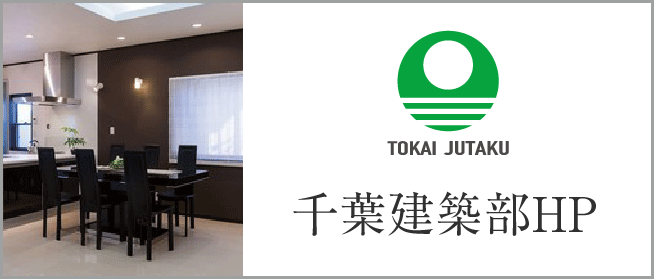
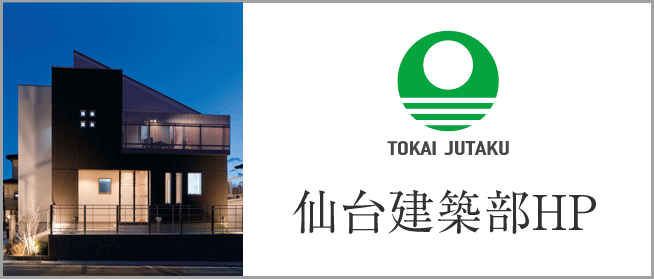


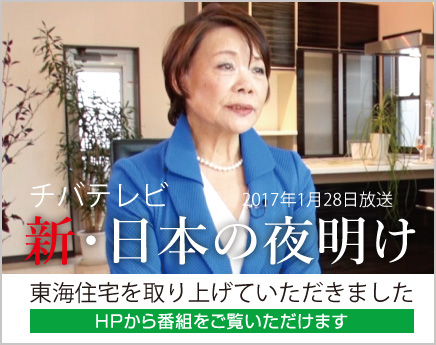

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア