台風19号での避難所体験 その2
前回は、台風19号上陸に際し、「警戒レベル4(対象地域住民の全員避難)」の指定を受けた知り合いのAさんが、避難所に落ち着くまでの体験をお話ししました。Aさんは両親と共に町会単位で行動し、避難所に到着。支給の毛布でスペースを作り、隣近所の人とまとまって、台風が過ぎるのを待ちました。今回はもう少し詳しく、避難所の様子を教えてもらうことにしましょう。
高齢者や身体が不自由な人は教室を利用
Aさんの住む市でも高齢化は進んでおり、避難所にはたくさんのお年寄りがやってきました。元気な人は自分で床に毛布を敷いて、座ったり、寝るなどして過ごしていたそうです。ただ、足の悪い人は少なくなく、床に座ることができず、パイプ椅子を利用していました。そのため、市では高齢者や身体の不自由な人には、体育館とは別に教室を用意。職員の呼び掛けに応じ、何人かはそちらに移って行ったそうです。
体育館の床は思った以上に硬く、また、つかまり立ちできるようなところもありません。トイレに行くにも大変そうだったといいます。そのような状況からか、高齢者や身体の不自由な人の避難場所は、トイレに近いところに設けられました。
また、現在、風邪などの病気にかかっている人に対しても、別に避難場所(教室)を設置。これは避難所での感染を防ぐためです。Aさんも、そのことは気になっており、避難所では帰宅するまでマスクを着用していました。
もうひとつ、Aさんが気になったのは、トイレに向かう廊下。中でも体育館の入り口付近は雨で滑りやすくなっており、町会の人が転んだからです。Aさん自身も家庭科室に行く途中、ここでバランスを崩したため、「どうにかならないかな?」と思っていました。このまま朝まで滞在するとなると、特にお年寄りやトイレの近い人が、足を滑らせて怪我をするかもしれません。
その後すぐに、滑りやすい場所には段ボールが敷き詰められました。そのままの状態より、格段と歩きやすくなり、Aさんはホッとしたそうです。
子どものいる家庭は、近くの保育園に移動
しばらくすると、近くの保育園も避難所になるとのことで、小さな子どものいる家族は、そちらへ移動。何もない、殺風景な体育館より、保育園の方が子どもも落ち着くのでは?との配慮でしょうか。園長さんがワゴンで迎えに来ていました。
夕食は18時からということで、Aさんをはじめ、ボランティアの人たちは、16時頃からアルファ米( α米 )のお弁当作りを開始。避難者が増え、近くに新たな避難所ができたこともあり、500食が必要になったそうです。無事に配布が終わると、現場責任者である小学校の副校長から、「消灯時間は9時半」とアナウンスがありました。
普段の生活からは考えられない就寝時刻ですが、Aさんは毛布の上に横になり、スマートフォンで台風関連のニュースを見ていたそうです。10時頃、外の様子を見に行くと、風は吹いているものの雨は小降り状態。「明日、早くには帰れそうだな」と室内に戻ると、緊張も手伝ってか、うたた寝をしてしまったそうです。
それから1時間ほど、Aさんは母親の「家に帰るよ」の声で目を覚まします。どうやら避難解除が出たようで、周囲を見渡すと、人も大分減っていました。すぐに荷物をまとめて、知り合いの車に分乗して帰宅。日が変わる頃、自宅に戻ったそうです。幸いなことに、町内には浸水や風などの被害はありませんでした。
避難所を体験してわかったこと
Aさんは「避難所に居たのは半日ほどだったから、役に立たないかも」とおっしゃいましたが、体験を聞いて、いろいろと気付いたことがありました。
・飲み物はできる限り、多目に持っていく(食事の際に500ml1本では心もとない)
・お菓子や日持ちのよいパンは持参(食事はパック詰めのおこわ(アルファ米( α米 ))ひとつなので、男性や育ち盛りの子どもには物足りないケースも考えられる)
・厚地のピクニックシートは必須(体育館の床は毛布を敷いても硬く、寝心地が悪い。また、寒い時期だと防寒のためにも必要)
・情報収集のためにも、スマートフォン用充電器は必要不可欠(スマートフォンなどを充電できるところはない)
・懐中電灯を忘れずに(消灯時間が早いので、役に立つ)
・マスクは必ず持参する(避難者の中には、風邪を引いている人もいる。また、体育館には埃っぽい場所もあるため)
・避難所へは早めに行く(警戒レベル3になったら、いつでも動けるように。人数が多くなると、他の避難所へ回らなくてはならないことがある)
自治体によっては、配給の内容も違うと思われますが、Aさんの話は大変参考になりました。できれば、災害による避難はしたくないものです。しかし、昨今の気象状況を見ていると、遭遇する可能性が高いことは否めません。
特に賃貸に一人暮らしの人は、避難所の場所を知らないことも多いといいます。普段から自分の住むエリアのハザードマップ、避難場所を確認し、いざというときは迅速に行動できるようにしておくといいでしょう。






















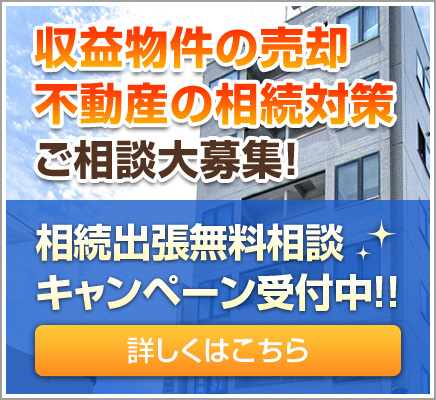
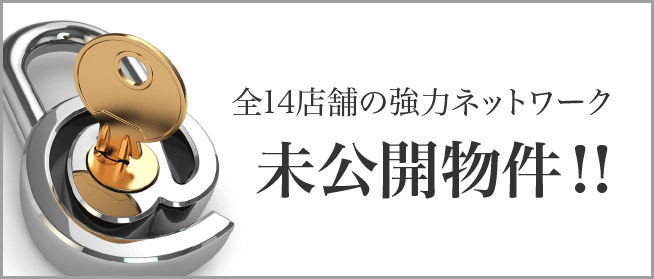
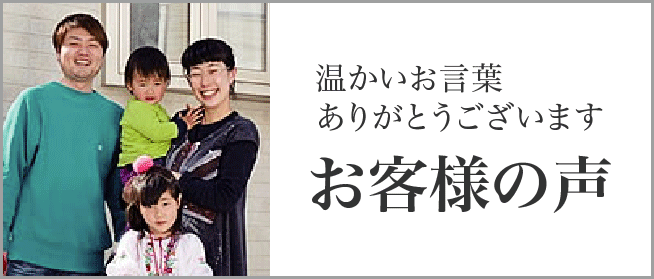



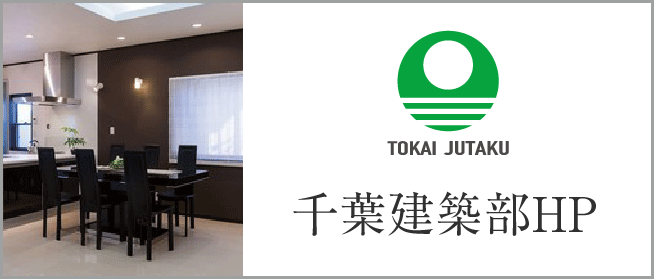
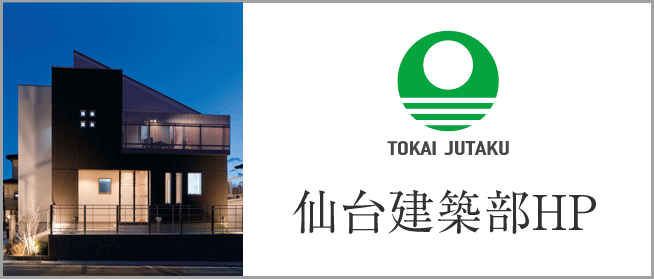


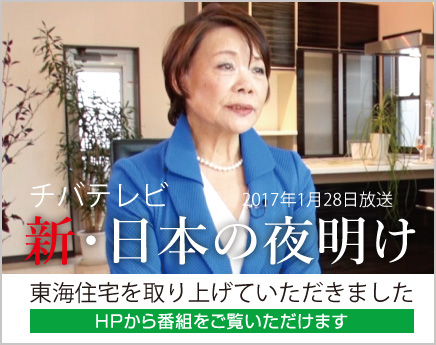

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア