「耐震改修工事助成金」について
地球に住んでいる限り、自然災害は避けて通ることができません。台風、ハリケーンをはじめ、山火事、川の氾濫、津波、火山の噴火など、世界各国で様々な災害が起こっています。地震もそのひとつですが、特に日本には地震が多く、過去にも「阪神淡路大震災」「東日本大震災」、近年では「熊本地震」「北海道胆振東部地震」が発生し、大きな被害が出ました。
それに対して行われているのが「耐震工事」です。これはビルや大きな建物だけでなく、住宅にも当てはまります。しかし、一般住宅で耐震診断・工事を行った場合、100万円以上かかることも少なくありません。そのため、「耐震改修をしたくてもできない」というケースもあるようです。そこで利用したいのが、国と自治体が行っている「耐震診断・耐震工事」の補助金制度です。これを用いれば、工事費用などが軽減されますから、チェックすることをおすすめします。
耐震化に対する助成制度の基礎知識
建築物の耐震改修を促すため、国や地方公共団体では、「耐震診断」「耐震改修」に対する支援を実施しています。そのひとつとして、以下を行う際には、補助制度が準備されています。
・耐震診断
・耐震改修設計
・耐震改修工事
助成される金額については、建物の規模や用途、建築地といった条件により変動。関連法規の改正などがあれば、補助対象建築物、補助割合も変わります。また、地方公共団体により対応も異なり、特に以下の点には注意が必要です。
・補助金申請は、耐震診断、改修設計、改修工事に着手する前に行い、交付決定通知を受けてから契約を締結しなくてはならない場合がある。
・補助金を申請する際には、第三者評価機関による耐震診断判定、耐震補強計画判定が必要な場合がある。
・補助金交付には領収書収書が必要。など
なお、ほとんどの自治体で補助金制度を利用していますが、すべてで行われているわけではありません。耐震工事を考えているのであれば、まず、自分の住んでいる自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
住宅の耐震改修工事の助成例
各自治体で行われている耐震診断・改修工事の助成例
それでは、現在、行われている「耐震診断・改修工事の補助金制度」の例を見ていきましょう。たとえば、東京都練馬区では住宅(戸建住宅、長屋、小規模な共同住宅)の耐震改修工事などを助成しています。助成対象を見てみると、「住宅が練馬区内にあること」「昭和56年(1981年)5月以前に建築された、現在の耐震基準を満たさない住宅であること」「住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満・2階以下。※住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限る)であること)となっています。
助成金額は耐震診断(一般診断又は精密診断)が費用の3分の2(8万円が限度)、実施設計は費用の3分の2(22万円が限度)、耐震改修工事で費用の3分の2(100万円が限度)です。なお、所有者が居住している戸建住宅で、世帯全員が住民税非課税の場合、費用の5分の4(120万円が限度)になります。また、耐震改修工事(練馬区緊急道路障害物除去路線沿道(地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、練馬区地域防災計画に位置づけられる路線)の戸建住宅の場合、費用の5分の4(120万円が限度)を助成されるそうです。
次に立川市の「耐震改修等工事助成」を調べると、市の助成を受けて実施した耐震診断の結果、耐震性能評価(上部構造評点)が1.0未満と診断された住宅についての耐震改修等工事に補助金がでます。金額は以下の通りです。
・補強設計及び工事監理:耐震性能評価を1.0以上とする補強設計及び工事監理に要した費用の2分の1(限度額10万円)
・耐震改修工事:補強設計に従い実施された改修工事に要した費用の2分の1(限度額50万円、高齢者世帯又は障害者世帯の場合は80万円)を助成。
これが府中市になると、次のような条件となっています。
・耐震診断:対象要件は木造住宅であって、昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建てまたは、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること、市税等を滞納していないこと。助成額は耐震診断費用の3分の2(限度額12万円)。
・耐震改修:対象は木造住宅耐震診断の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修。条件は所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること、市税等を滞納していないこと。助成額は耐震改修費用の2分の1(限度額110万円)。
このように、各自治体によって内容や助成額はまちまちです。とはいえ、自宅の耐震化を考えており、補助を受けられるのであれば、検討してみることをおすすめします。
住宅の除去にも助成金が公布される
府中市の場合、住宅を除去する場合にも助成金を受けることができます。
・耐震除却:木造住宅耐震診断の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅全部の除却。条件は所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること、
市税等を滞納していないこと。助成額は除却費用の2分の1(限度額50万円)。
また耐震シェルターの設置も補助されています。
・耐震シェルターなどの設置:木造住宅耐震診断の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置。対象条件は、65歳以上の方のみで構成された世帯、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級を所持する人のいる世帯で市税等を滞納していないこと。助成額は設置費用の4分の3(限度額30万円)。
住宅除去や耐震シェルターに加え、たとえば埼玉県狭山市では、地震の際に倒壊が予想される危険なブロック塀などの改修工事に対し、補助制度を行っています。補助の対象となるのは、市内の幅4m以上の道に接して建つ、道路からの高さが1m以上のブロック塀で、傾いている、大きなひび割れがある、ぐらつきがある、法律で定められた基準に構造が合わず強度が不足しているなどの、危険なブロック塀など。対象となる工事は、ブロック等の全部又は一部を撤去する工事の費用と、撤去工事後に安全なフェンス等を新設する工事の費用です。補助金の申請ができるのは、市内の危険なブロック塀等を所有、または管理する人(法人を含む)。ただし、市税を滞納している方は申請不可。補助金額は以下の通りです。
・撤去工事に対する補助額:撤去工事費と撤去する塀の長さ1m当たり5千円を掛けた額と比較して少ない額、かつ限度額10万円
・新設工事に対する補助額:新設工事費と新設する塀の長さ1m当たり2万円を掛けた額と比較して少ない額、かつ限度額20万円(補助額算定の塀の長さは、撤去する塀の長さを上限とする)
今後のことを考えると住居の耐震化、危険ブロックの除去・改修は欠かせません。助成金を上手に利用して、安全な暮らしを送りたいものです。






















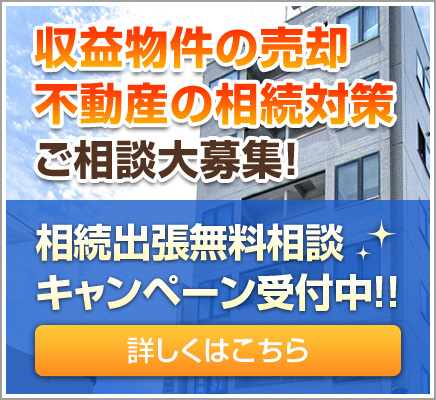
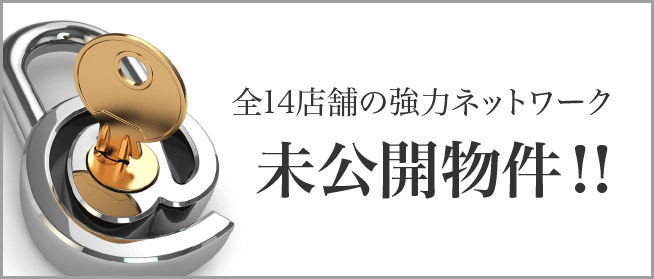
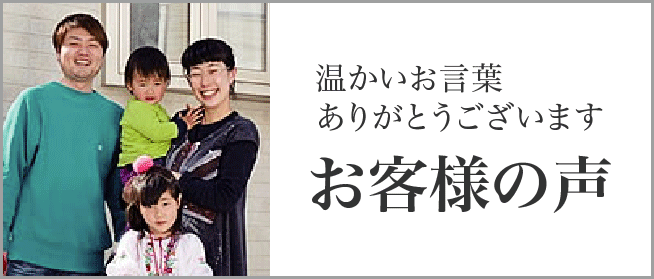



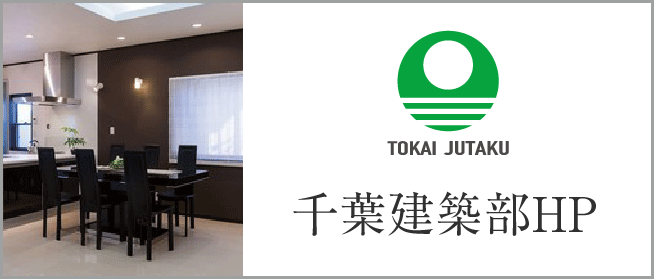
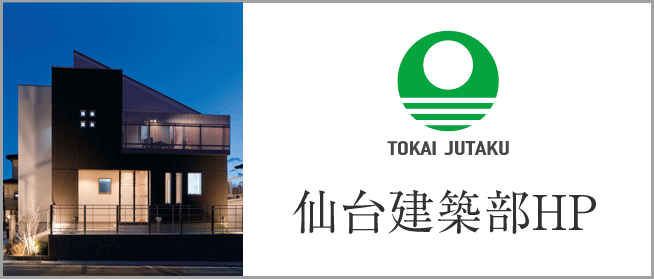


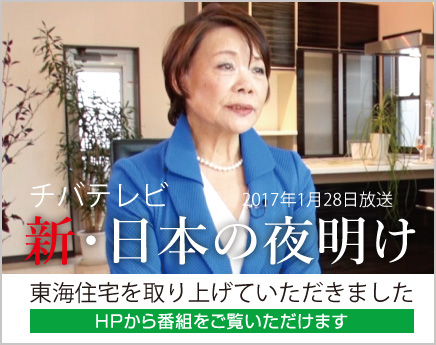

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア