大掃除が楽しくなる? 「大掃除トリビア」
早いもので2017年もあと1ヶ月となりました。
「いいことがたくさんあった」人がいれば、「ちょっとハードな年だった」と思う人もいるでしょう。
さて、年末といえば「大掃除」。
最近は便利で多種多様な掃除用具が増えたせいか、日頃の掃除が行き届き、わざわざ家族総出の大掃除をする家は少なくなったといいます。
とはいえ、新たな年を気持ちよく迎えるため、普段掃除をしないところなどに手を入れてみることをおすすめします。ただ、ちょっと怠けていたので、それなりに頑張らなくてはという人もいるでしょう。そこで今回は、掃除が楽しくためになる? 大掃除の薀蓄を集めてみました。
「掃除」は神事から始まった?
現在は「部屋をきれいにする行為」として認識されている「掃除」ですが、その始まりは神事にあったといわれています。
たとえば、普段何気なく使っている「箒」は、神事にかかわる神聖な道具のひとつであり、「箒神」という神様が宿ると考えられていました。
この神様は、「産神(出産にかかわる神)」のひとつで、「掃く」「掃き出す」という行為が出産と結びつき、安産の守り神とされています。
そのため、箒で産婦のおなかをなでる、足許に逆さに立てれば、お産が軽くなると言い伝えられています。
また、玄関に箒を逆さまに立てると、長居の客を帰す=家から掃き出すことができるという話もあります。
西洋において箒は、魔女の乗り物として有名ですが、日本ではとても神聖なものとして使われていたのです。
日本において掃除の概念が登場するのは、古事記に記録が残っていることから7世紀頃だといわれています。
平安時代になると、宮中では新年の安泰と五穀豊穣を願い、新しい年を迎えるために家の内外を清めるための「煤払い」も始まり、箒は掃き掃除の道具としても用いられるようになりました。
また、庶民の間に掃除という習慣が根づいたのも、この頃です。
ただし、ほとんどの庶民は土間で生活していたため、掃除は煮炊きを行うカマドの周りが中心でした。
鎌倉時代には、禅宗が修行の一環として掃き掃除を行った際、箒が使われていたようです。
室町時代になると「箒売り」という職業が登場していることから、普段から掃除が行われ、箒が欠かせない道具になったことがわかります。
「煤払い」から「大掃除」へ
江戸時代になると、今の大掃除に繋がる「煤払い」が行われるようになります。
先述したように、煤払いはその年の汚れを除き、新しい年に歳神を迎える準備をするために行われていました。
江戸時代になると年間行事のひとつとなり、江戸城(江戸幕府)では12月13日が「煤払いの日」と定められ、「御事納」「御煤払」「煤取り」「煤掃き」「煤納め」と呼ばれる大掃除が行われるようになります。
江戸城大奥、武家屋敷では、煤払いの後、畳替えが行われました。
なお、当時の煤払いは、現代のように「家をきれいにしてお正月を迎える」というより、信仰的な意味合いの強い行事でした。
12月13日に行われたのは、正月を迎える「物忌み」の始まるのが、この日だったからです。
なお「物忌み」とは、祭祀や神事、または凶事から免れるため、ある期間不浄を避け、食事や行動を慎むことをいいます。
幕府の行事に習うように、商家や民家でも12月13日に煤払いが行なわれていました。
庶民の間では、物忌みの始まりという目的以外に、徒弟・奉公人たちが新年までに里帰りできるよう、この日に煤払いをしたともいわれています。
結構、大変な仕事だったようで、作業の合間にはにぎり飯や煮しめ、おやつも出されたそうです。
また煤払いが終わった後、商家では、疲れた体を癒す「鯨汁」が振る舞われたという記録が、数かずの川柳や書物に残っています。
「江戸中で五六匹喰ふ十三日」
これは煤払いの日には、鯨が5、6匹分食べられる~そのくらい人々が働き、賑やかな一日だった様子を描いた川柳です。
煤払い後は胴上げ大会? まるで日本シリーズの優勝フィーバー?
畳替え、鯨汁のほかに、煤払い終了後には、ある行為が行われていました。
それは「胴上げ」です。
胴上げするようになったきっかけはわかっていないようですが、煤払いが終わると、商家はもちろん、なんと大奥においても、誰かれ構わず胴上げするのが慣わしになっていたといいます。
大奥では奥女中のほかに、武士も胴上げの標的になっていたそうです。
当時の様子を描いた絵の中には、武士や男性を胴上げするものが残っています。
ただ、その頃の女性もやはりメンクイだったようです。
「十二日 から色男 狙われる」
この川柳からは、女性たちが、前日に胴上げするイケメンを物色(?)していたことがわかります。
「美男」ともてはやされていた男性は、戦々恐々だったことでしょう。
そのため、「狙われている」と感じた男性は、胴上げされないよう、逃げ回っていたといいます。
江戸時代の煤払いは、当時はイベントのひとつだったのかもしれませんね。






















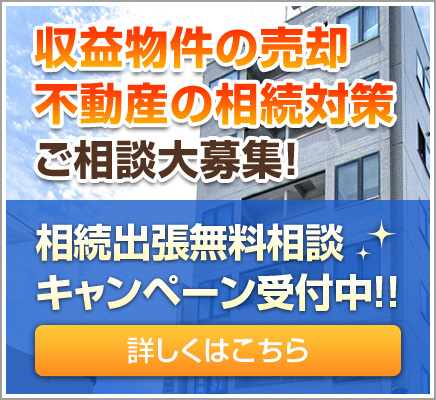
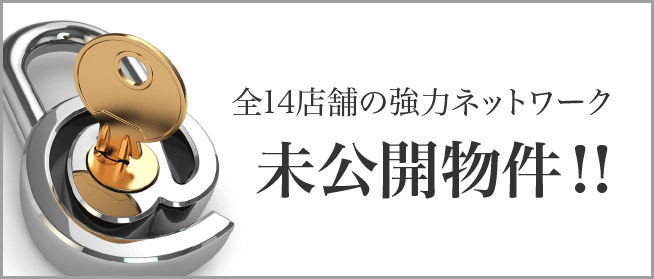
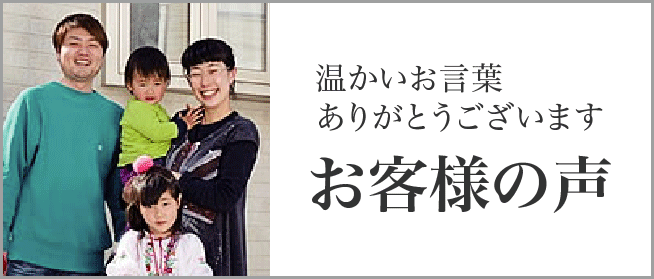



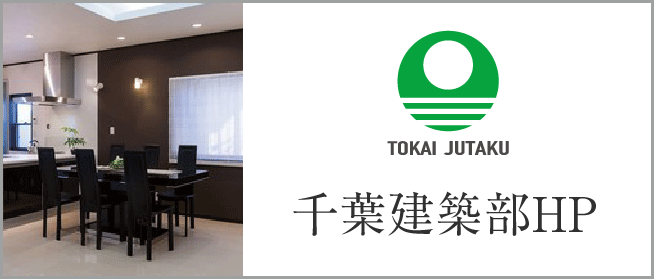
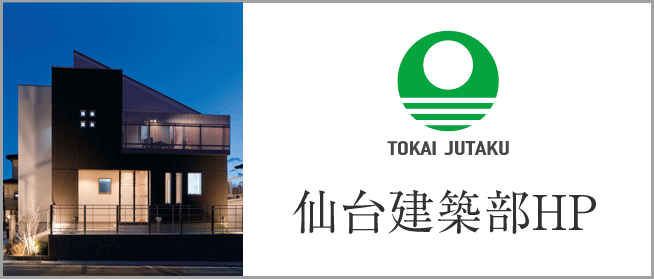


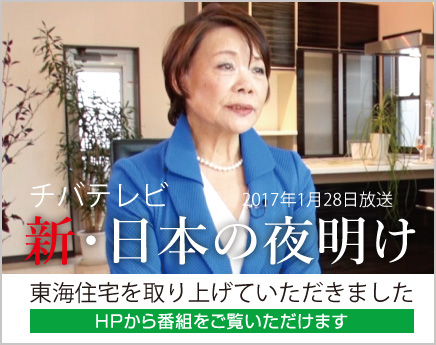

 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる リフォームする
リフォームする 物件を探す
物件を探す 売却の相談
売却の相談 家を建てる
家を建てる 千葉で建てる
千葉で建てる 宮城で建てる
宮城で建てる リフォームする
リフォームする 千葉でリフォームする
千葉でリフォームする 宮城でリフォームする
宮城でリフォームする 店舗一覧
店舗一覧 千葉エリア
千葉エリア 栃木エリア
栃木エリア 福島エリア
福島エリア 仙台エリア
仙台エリア