2025.04.28
共通
Column 【2025年4月】建築基準法改正の6つのポイントと不動産市場に与える影響を紹介
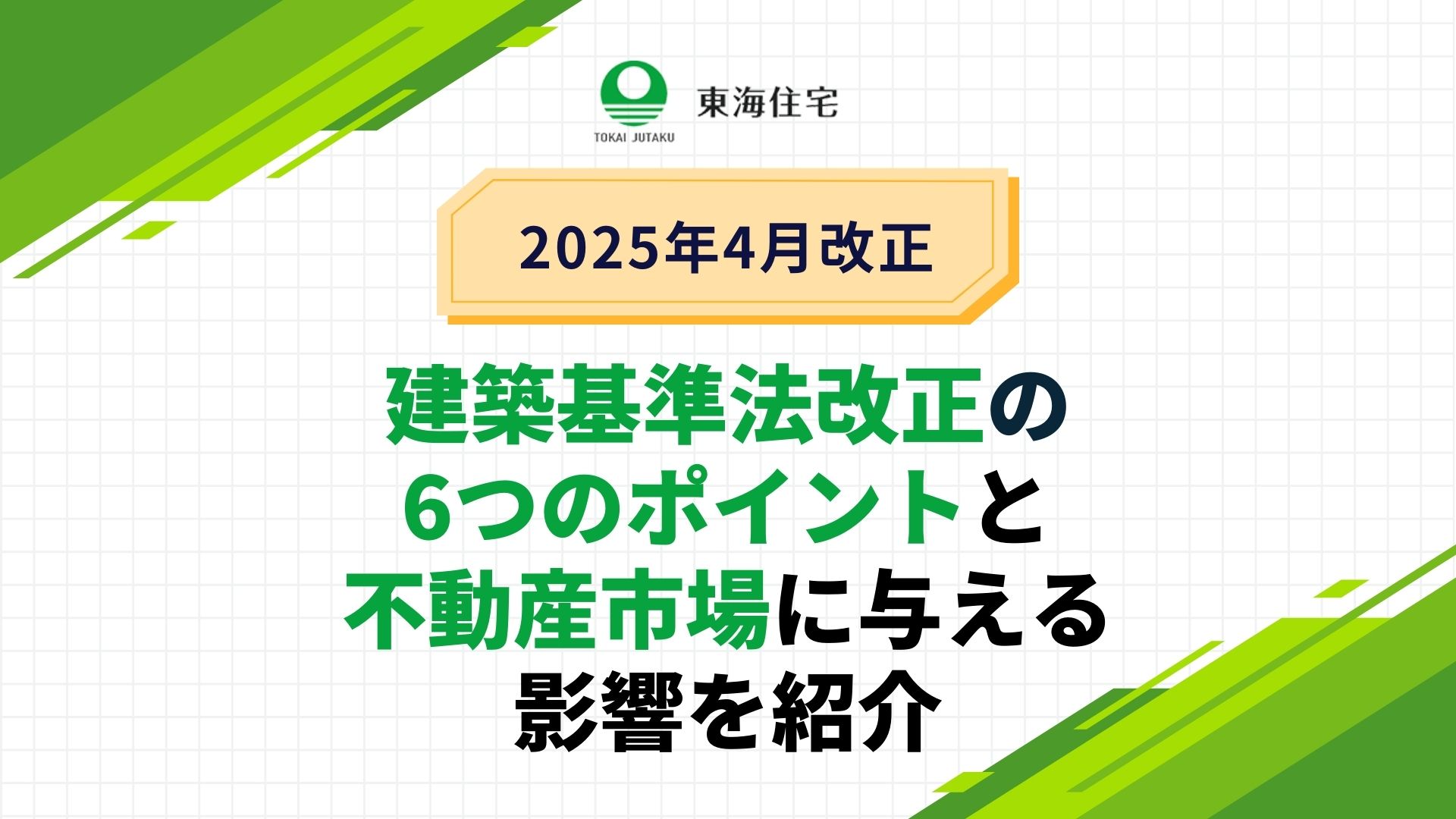
建築物の安全性や省エネルギー性能の向上を目的として「建築基準法」は、2025年4月1日に改正されました。建築基準法の改正は、住宅の新築やリフォームだけでなく、不動産市場全体にも影響を与える可能性があります。
そこで本記事では、建築基準法改正のポイントと不動産市場に与える影響を解説します。改正内容を正しく理解し、所有されている不動産の方法を検討する際の判断材料にしてください。

【2025年4月】建築基準法改正の6つのポイント
1. 4号特例の縮小
純然の4号特例は、小規模な木造建築物などに対して、建築確認の審査を一部簡略化する制度でした。しかし改正後は対象範囲が見直され、木造では平屋かつ延床面積200㎡以下の建築物のみが特例の対象となります。
これまで特例対象だった木造2階建てや、延床面積200㎡を超える平屋などは「新2号建築物」に分類され、今後は構造計算に関する書類提出や審査が必要です。そのため、小規模な住宅の新築や増改築においても手続きが煩雑化して、設計や審査にかかるコストが増加する可能性があります。
2. 木造建築物の構造基準変更
3階建ての木造建築物は、従来の建築基準法では高さ13mまたは軒高9m以内の場合のみ簡易な構造計算で安全性を確認できました。しかし、改正後は基準が見直され「高さ16m以下」に範囲が拡大されています。
一方で4階建て以上の場合は、高さに関わらず「許容応力度等計算」などの高度な構造計算が求められるようになりました。
3. 大規模木造建築物の防火規定変更
延床面積3000㎡を超える木造建築物において、従来は耐火性の観点から木材を石膏ボードなどで覆う必要がありました。しかし今回の改定により、適切な防火措置を講じることを前提として、柱や梁などの構造材を木材のまま見せる「現し(あらわし)」での設計が可能になります。
デザインの自由度が増す一方で、今後は安全性を確保するための防火対策が、より一層重要になるでしょう。
4. 省エネ基準の適合義務化
これまで、省エネ基準への適合義務は一部の大規模建築物を除き努力義務でした。しかし、改正後は全ての新築建築物に対して、国が定める省エネルギー基準への適合が義務付けられます。
そのため省エネ基準を満たさない設計の建築物は、今後は建築確認が受けられません。住宅の断熱性能や設備のエネルギー効率が向上する一方で、断熱材の追加や高効率設備の導入などにより、建築コストが増加する可能性があります。
5. 中層建築物の耐火性能基準の緩和
5階から9階建て程度の中層建築物において、火災発生から建物の倒壊抑制に必要な時間を検証し、90分間の耐火性能が確保できれば木造での建築が可能となりました。これまでの基準では厳しい制限がありましたが、耐火性能基準が緩和されたことで、都市部などでも木材を活用した中層建築物の建設が促進されることが想定されます。
6. 既存不適格建築物への基準一部免除
既存不適格建築物とは建築当時は適法だったものの、その後の法改正により基準に適合しなくなった建築物を指します。今回の改正により、増改築や用途変更を行う際に現行の耐震基準を満たしていなくても、一定の条件下で基準の一部適用を免除する規定が設けられました。
今後は耐震改修などが進みにくかった空き家や、古い建物の再利用・リノベーションが促進されることが期待されます。
建築基準法の改正が不動産市場に
与える影響【早期売却がおすすめ】

2025年4月の建築基準法改正における省エネ基準の適合義務化により、断熱性能が高くエネルギー効率の良い住宅の需要が高まるでしょう。一方で現行の基準を満たさない住宅については、将来的な資産価値維持のための適切な情報収集が、より重要になっていきます。また4号特例の縮小により、小規模な住宅のリフォームや増改築のコストが増加する可能性があります。
このような状況下で不動産を売却するなら、建築に詳しく合法的な改修方法を買主に説明できる不動産会社に依頼するのがおすすめです。不動産会社「東海住宅」は建設会社でもあるため、技術的なアドバイスも行えます。法改正の影響を踏まえた販売戦略をご提案し、お客様の不動産売却をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。






























